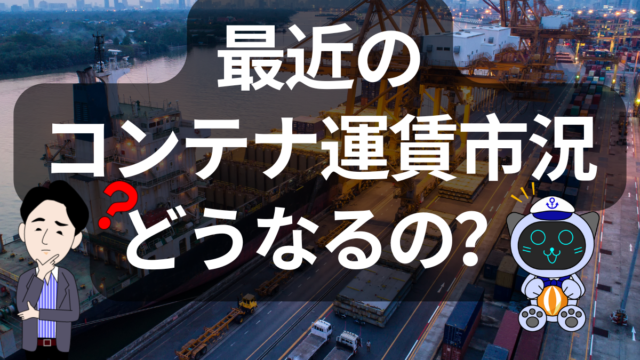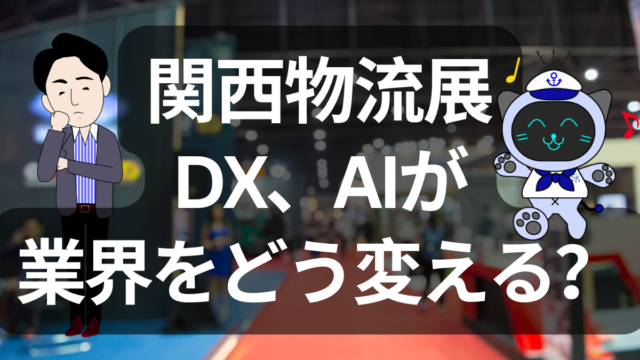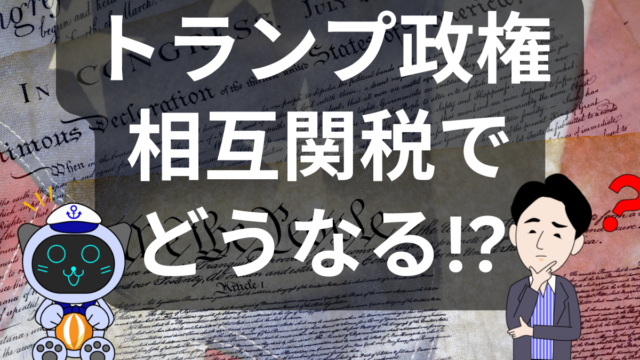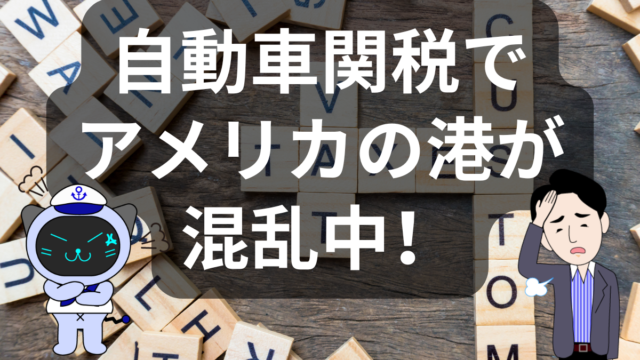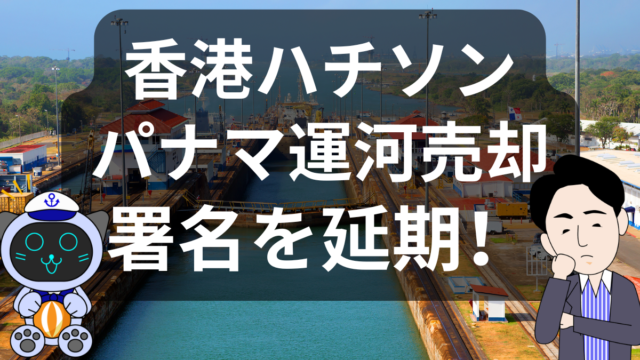投稿日:2025.04.16 最終更新日:2025.04.16
【2024年問題が本格化】海上コンテナのドレージ手配が困難に。物流の現場で何が起きているのか?

今回は、「海上コンテナのドレージ輸送に2024年問題の影響が顕在化」というニュースをテーマにお話しします。
CONTENTS
そもそも「2024年問題」とは?
物流業界における「2024年問題」とは、ドライバーの労働時間規制の強化により、トラック運転手の稼働時間が短縮されることで、輸送能力の不足が深刻化する問題を指します。
この規制は2024年4月に本格的にスタートしました。 そして今、施行から1年が経過した2025年4月現在、その影響が目に見える形で顕在化しています。
ドライバー不足で「ドレージ手配ができない」事態に
特に影響が大きいのが、海上コンテナのドレージ(陸上輸送)です。
たとえば、東京港ではコンテナ輸送の車両手配に1ヶ月前の予約が必要という声も出ています。
これは非常に深刻です。 なぜなら、コンテナ船は遅延が多く、検査や天候の影響で納品スケジュールが不確定な場合がほとんどだからです。
「1ヶ月前に予約しても、その日に輸送できる保証がない」という状況は、現場にとって極めて非現実的。 物流業者や荷主にとって非常に大きなストレスになっています。
業界からの撤退も増加。2030年には輸送力34%不足との試算も
この厳しい環境下で、ドレージ業者の廃業が増加しています。 国の試算では、2030年度にはトラック輸送力が34%不足するとのこと。
つまり今後、「モノが届かない時代」が加速することが明らかです。
特に港から倉庫への輸送が滞ると、輸入業務全体への影響は避けられません。
しかし課題も…
一部のドレージ業者では、人手不足への対応として運賃の値上げ(約5〜15%)に踏み切っています。
とはいえ、長年にわたり不当に安く抑えられてきた背景があり、現在の値上げ幅ではまだ厳しいという声も。
「値上げすれば他社に切り替えられてしまう」
こうした事情で、業者側も非常に苦しい立場に置かれています。
ドライバーの高齢化と後継者不足という構造的課題
さらに根本的な問題として、ドライバーの高齢化と若手の不足があります。
かつては「稼げる仕事」として人気がありましたが、現在は労働時間の制限で収入が伸びづらく、若者からは敬遠されがちです。
また、けん引免許の取得が難しく費用も高額であることも参入障壁となっています。
外国人ドライバーの採用も検討されていますが、日本語の標識・法規の理解や運転技術のハードルが高く、即戦力としては厳しいのが現状です。
【現場の声】ショートドレージが確保できないとどうなる?
実際に私自身が体験したケースをご紹介します。
輸入貨物がX線検査対象となり、港から検査場までのショートドレージが必要となりました。 しかし、その手配ができず、検査を受けられずにデマレージ(保管料)が発生してしまいました。
「輸送できない=コストが増える」という悪循環が、今後さらに加速する恐れがあります。
荷主の皆様へ:値上げの背景には切実な現実があります
このブログを読んでくださっている荷主企業の方がいらっしゃれば、 ドレージ業者からの値上げ要請には耳を傾けていただきたいと思います。
単なる「値上げ」ではなく、そこには人手不足と業界構造の問題があるという現実を、ぜひご理解いただければ幸いです。