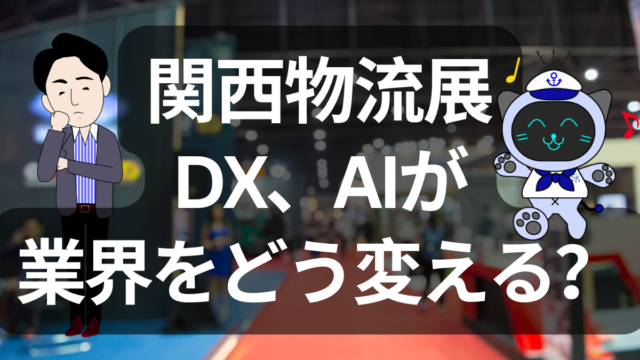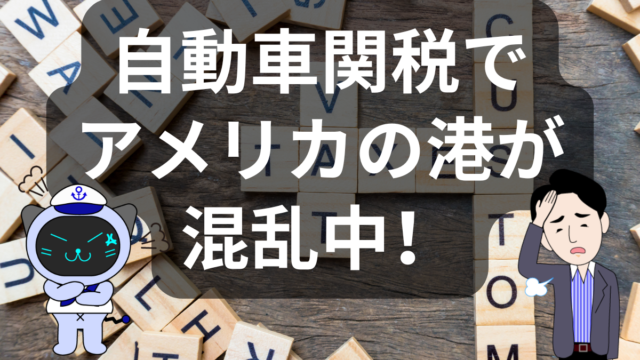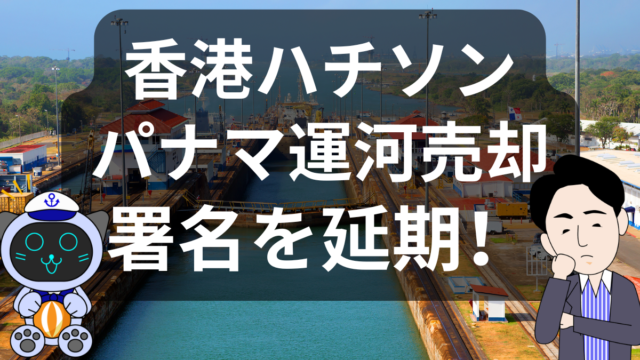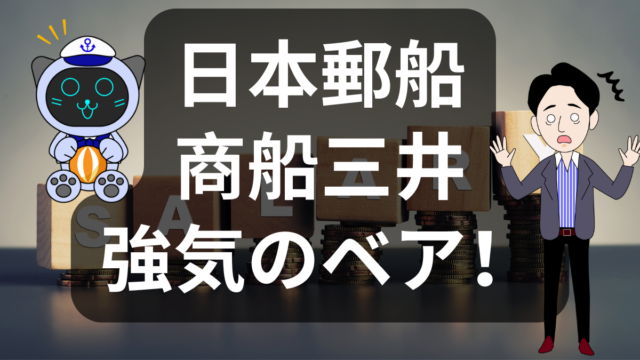投稿日:2025.04.08 最終更新日:2025.04.09
【物流現場のリアル】トランプ大統領の相互関税とこれからのサプライチェーン
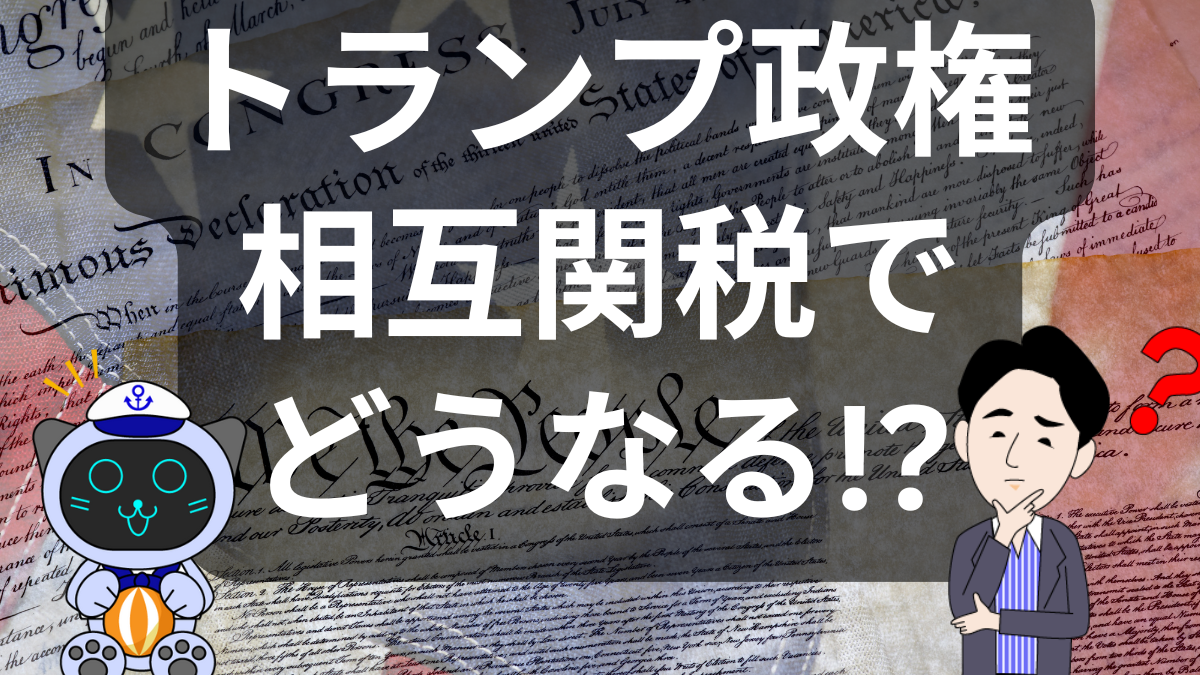
今日は最近話題の「トランプ大統領の相互関税」について、物流の現場から見たリアルな視点をお届けします。
CONTENTS
相互関税、結局どうなる?
結論から言えば、「何が起こるか分からない」。 この一言に尽きます。現在、物流業界ではまだ大きな物量の変化は見られず、現場は「静観」の姿勢をとっています。
しかし今後、特に中国からアメリカへの輸出に大きな影響が出ると感じています。現在、中国製品には20%の関税がかけられ、さらに追加で34%。つまり合計で54%という高率関税が課される見込みです。
“5割増し”の関税となれば、さすがに輸出の減少は避けられません。これが私たち物流現場での肌感覚です。
サプライチェーンはすぐには動かない
「じゃあ中国以外に切り替えればいいのでは?」と思うかもしれませんが、現実はそんなに簡単ではありません。
たとえば、アメリカの工場で使われているパーツを別の国から調達しようとすると、 スペックの適合や製造体制の構築など、様々な障壁が立ちはだかります。
サプライチェーンの変更には時間もコストもかかる。それが現実なのです。
関税はアメリカ経済にどう響くのか?
この高関税政策は、当然アメリカ国内にも影響を与えています。 一部ではデモも起きており、インフレ加速の懸念もあります。
とはいえ、今のところ「やっぱやめます」的な政策転換は見えません。
企業にとって厳しいのは、関税分を価格に転嫁しづらいという点です。 日経新聞に紹介されたサントリーの社長も、 「ウイスキーに関税がかかってもすぐに値上げは難しい」とコメントしていました。
つまり、企業側が“我慢”するケースが増え、 利益が圧迫 → 株価に反映という構図が見えてきます。
ロジスティクス現場の視点で見るこれから
物流業界では、海上運賃や取り扱い数量(ボリューム)などのデータを日々チェックしています。
関税の影響は数か月遅れて数字に現れるため、 今後、夏〜秋にかけて大きな変化が出てくる可能性が高いと見ています。
今は静かに見えていても、水面下では確実に変化が始まっている。 この変化をどう読み解くかが、これからのサプライチェーン戦略において非常に重要です。
引っ越しから学んだ“現場を知る大切さ”
ちなみに私事ですが、現在大阪に引っ越すため物件探しをしており、 京都の実家に滞在中です。
不動産屋さんのサービスを受けて感じたのは、「誰から買うか」が大事ということ。 物件自体よりもその土地をどれだけ知っているかが、大きな価値になるんですよね。
これは物流にも通じます。 タイの物流事情について、現地を知っているからこそできる提案があります。
“ローカルを知ることの重要性”を、家探しを通じてあらためて実感した次第です。